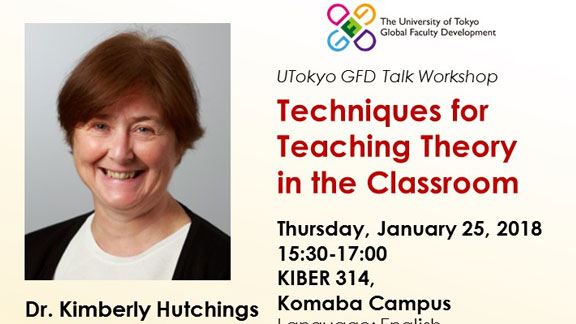東京大学駒場のグローバルFD部門主催で、下記2つのワークショップが開催されます(12月5日、12月7日)。
ご関心のある方は、詳細をご確認の上ご参加ください。
=1つめ(12/5開催)=
As part of our Global FD initiative at UTokyo, we are hosting a seminar on “Incorporating Student Research into Teaching, or A Tale of 23, 236 Mulinia?” on Tuesday, December 5 2017, 17:00-18:30. The lecturer will be Prof. , Patricia Kelley, Professor Emerita of Geology, Department of Earth and Ocean Sciences, University of North Carolina Willmington.
Please come and join us!
Details about the seminar are listed below:
Title: “Incorporating Student Research into Teaching, or A Tale of 23,276 Mulinia”
Students learn best by doing: when they apply what they have learned to real-world problems, for instance by conducting research. When we incorporate student research in our teaching, students benefit from improved research skills and life skills (problem solving, critical thinking, communication), as well as enhanced personal development (self-confidence, ability to work independently and in teams). At many institutions, these benefits are reserved for a select group of high-achieving students who work individually with faculty members. However, research-embedded courses can make such benefits available to a wider range of students. This lecture will discuss best practices in experiential learning and the incorporation of research in teaching by focusing on courses with embedded student research. Guidelines will be presented for how to plan and execute a course-embedded research project, along with ways to overcome the challenges involved in adopting this mode of teaching.
Date: Tuesday, Dec 5 2017, 17:00-18:30
Place: KIBER 314 Komaba Campus The University of Tokyo
Eligibility: All faculty, staff and students welcome!
Language: English
Admission: Free
Registration: Encouraged here but walk-in also welcome!
Inquiries: GFD committee gfd-tokyo@adm.c.u-tokyo.ac.jp
Event URL: http://www.gfd.c.u-tokyo.ac.jp/event/20171205-00001158.html

=2つめ(12/7開催)=
As part of our Global FD initiative at UTokyo, we are hosting a workshop on “Controversial Topics in the Classroom:”(How) do we dare discuss them?” on Thursday, December 7 2017, 15:00-16:30. The lecturer will be Prof. , Patricia Kelley, Professor Emerita of Geology, Department of Earth and Ocean Sciences, University of North Carolina Willmington.
Please come and join us!
Details about the workshop are listed below:
Date: Thursday, Dec 7 2017, 15:00-16:30
Place: KIBER 314 Komaba Campus The University of Tokyo
Eligibility: All faculty, staff and students welcome!
Language: English
Admission: Free
Registration: Encouraged here but walk-in also welcome!
Inquiries: GFD committee gfd-tokyo@adm.c.u-tokyo.ac.jp
Event URL: http://www.gfd.c.u-tokyo.ac.jp/event/20171207-00001159.html