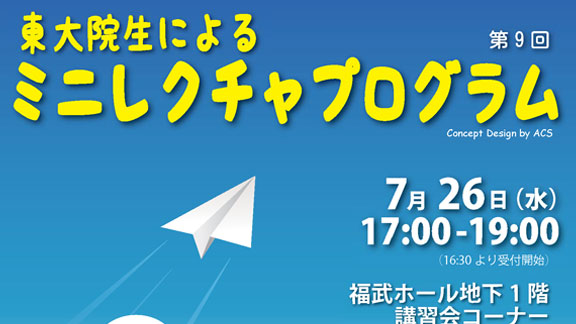先日終了しました下記のイベントにつき、当日の模様と、次回の予告について簡略ながらご報告します。
「インタラクティブ・ティーチング」Smallリアルセッション 第2回「90分授業のデザイン」
日時:2017年9月9日(土)13時~18時
場所:東京大学本郷キャンパス 工学部2号館92B教室
対象;若手大学教員、大学教員を目指す大学院生・PD(定員20名)
ファシリテーター:中村長史(東京大学 大学総合教育研究センター)
コメンテーター:栗田佳代子(東京大学 大学総合教育研究センター)
1.テーマ・目的
今回のテーマは、「90分授業のデザイン」でした。「学習者の学びが深まるような授業をデザインすることができるようになる」という目的のもと、より具体的には、①クラスデザインの意義やTipsを説明できるようになる(後述する事前課題に対応)、②クラスデザインシート(本講座で紹介している授業設計のフォーマット)を用いて授業を改善できるようになる(当日の内容に対応)といった到達目標を定めました。これらの目的・目標のもと、定員満席(20名)の参加を得て、開催されました。

当日の個人ワークの様子
2.概要
反転授業型の本イベントでは事前課題が設けられていました。当日は、事前学習の復習に続いて、サンプルのクラスデザインシートを改善する演習を行ないました。また、メタ振り返り会と題して、このイベント自体のデザインを振り返る機会を作りました。
(1)事前学習
動画「インタラクティブ・ティーチング」および書籍『インタラクティブ・ティーチング』(河合出版、2017年)の該当章(week4、4章)を視聴・読了してくることが参加者全員に課されました。また、希望者は、自分の授業のクラスデザインシートを作成・提出することができました。
(2)当日
【1】趣旨説明(13時~13時15分)
本日のプログラム全体の目的や構成、本イベントにおけるルールを確認した後、参加者同士の自己紹介を行ないました。
【2】事前学習の復習(13時15分~13時45分)
事前学習の復習についてグループワークを交えて行なうことで、知識の定着を図りました。ここでは、クラスデザイン一般における意義や注意点を中心に改めて確認しました。
【3】クラスデザインシート改善演習(13時45分~15時30分)
サンプルとして配布されたクラスデザインシートの優れている点と改善点とを指摘するグループワーク(ポスターツアー)を行ないました。事前課題とその復習で得た知識を実践できるようになることに、その狙いがありました。なお、ポスターツアーについては、動画week2の「4.ポスターツアー」や書籍『インタラクティブ・ティーチング』の31~33頁をご覧いただければ幸いです。
【4】まとめ(15時30分~16時)
まとめでは、本日学んだことや疑問に思ったことと、それを踏まえて翌日以降に各人の現場に持ち帰るものとを、グループワークや質疑応答を通して、確認しました。
(3)メタ振り返り会(16時30分~18時)
事前学習と当日のデザインについて、企画者側の設計意図、参加者側の感想を、時系列に沿って相互に話し合いました。この過程を通して、企画者側の工夫が功を奏した点、まだまだ改善が必要な点、その具体的な改善策がみえてきました。

当日のポスターツアーの様子
3.参加者の反応
今回の主対象は、若手大学教員、PD・院生でしたが、様々な大学等から、計20名の方々にご参加いただくことができました。満足度について5段階評価(際立って良かった、大変良かった、良かった、まあまあ、良くなかった)で尋ねたアンケートでは、44%の方が最高評価の「際立って良かった」、56%の方が次点の「大変良かった」と回答されました。今回より、アンケートの選択肢に「際立って良かった」を追加し、より厳しい基準で評価をいただくことにしましたが、一定の評価をいただけて安堵しております。更なる高評価を目指して、メタ振り返り会やアンケートで挙がった改善点を次回以降の企画・運営に活かしていく所存です。
4.次回予告
その次回は、12月に、同じく「90分授業のデザイン」をテーマとして、内容・時間を拡大して開催することを予定しております。詳細が決まり次第、お知らせいたします。皆様のご参加をお待ちしております。
参考情報
動画「インタラクティブ・ティーチング」
JREC-IN webサイト
東大FD webサイト
書籍『インタラクティブ・ティーチング』(河合出版、2017年)
https://www.kawai-publishing.jp/book/?isbn=978-4-7772-1794-6(河合出版webサイト)
中村長史
(「インタラクティブ・ティーチング」担当・特任研究員、本イベント・ファシリテーター)