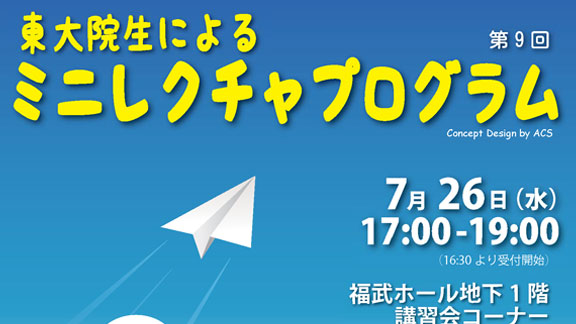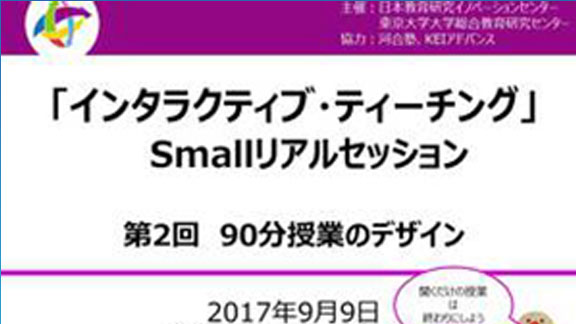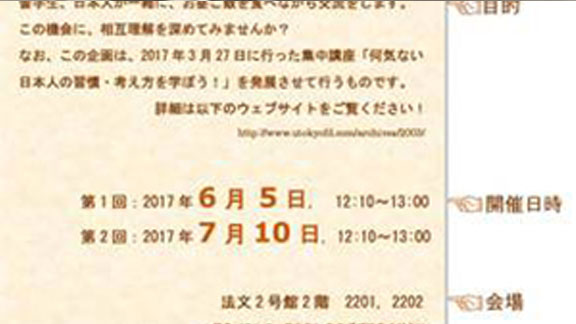さる8月20日(日)「インタラクティブ・ティーチング」Bigリアルセッション 第2回「ルーブリックを極める」を開催いたしました。当日の模様と次回の予定について簡略ながらご報告します。なお、より詳細な点については、前回同様、報告書を公開する予定でおります。また、東大TVにおいて、当日の模様が動画で公開される予定です。
1.テーマ・目的
今回のテーマは、評価の代表的手法の一つである「ルーブリック」でした。「学習者の学びが深まるようなルーブリックを作成・活用することができるようになる」という目的のもと、定員満席(80名)の参加を得ました。
2.概要
反転授業型の本イベントでは事前課題が設けられていました。当日は、事前学習の復習に続いて、ルーブリック一般の意義や注意点(総論)を確認し、参加者各自の文脈における意義や注意点(各論)にまで考えを深めました。
動画「インタラクティブ・ティーチング」および書籍『インタラクティブ・ティーチング』
(河合出版、2017年)の該当章(week6、6章)を視聴・読了してくることが参加者全員に課されました。
(2)当日
【1】趣旨説明(10時~10時15分)
本日のプログラム全体の目的や構成、本イベントにおけるルールを確認した後、参加者同士の自己紹介を行ないました。
事前学習の復習についてグループワークを交えて行なうことで、知識の定着を図り、セッション2以降に備えました。ここでは、評価一般における意義や注意点を中心に改めて確認しました。
サンプルのルーブリックを改善するグループワークを通して、ルーブリックを作成・活用する際の一般的な意義や注意点について確認しました。
セッション2で確認した一般的な意義や注意点を踏まえて、各自の文脈でルーブリックの作成や活用について検討を加えました。これまでの経験や属性に基づき、3つのセッションに分かれました。
セッションAには、ルーブリックを作成・活用した経験のあるメンバーが集まりました。まず、各自が持参したルーブリックについて、グループでの話し合いを通して改善するワークを行ないました。次に、ルーブリック作成や活用に際しての疑問点をグループで共有し、「Q&A集」(ポスター)を作成しました。
セッションBには、ルーブリックの作成経験はあるものの活用経験はない/作成経験のないメンバーが集まりました。まず、プレゼンテーションを評価するためのルーブリックをグループで作成し、それを用いて実際にプレゼンテーション(動画)を評価するワークを行いました。次に、各自の授業で使えそうなルーブリック作成を可能な範囲内で行ない、グループで改善に向けた意見交換をしました。
セッションCには、小中高校の教員が集まりました。まず、高校でのルーブリック活用の現状を確認した後、高校生のプレゼンテーション(動画)を配布されたルーブリックで評価しました。次に、各自のルーブリックを改善したり新たに作成したりした後に、グループで更なる改善に向けた意見交換をしました。
まとめでは、本日学んだことや疑問に思ったことと、それを踏まえて翌日以降に各人の現場に持ち帰るものとを、グループワークや質疑応答を通して、確認しました。
3.参加者の反応
様々な大学・高校・中学校・小学校・企業から、計80名の方々にご参加いただくことができました。満足度について5段階評価で尋ねたアンケート(有効回答数73)では、67%の方が最高評価の「大変満足」、32%の方が次点の「満足」と回答されました。2017年2月開催の第1回に続き一定の評価をいただけたものと安堵すると同時に、更なる高評価を目指して、アンケートで挙がった改善点を次回の企画・運営に活かしていく所存です。
4.次回予告
その次回は、2018年2月に開催を予定しております。詳細が決まり次第、お知らせいたします。皆様のご参加をお待ちしております。
中村長史
(「インタラクティブ・ティーチング」担当・特任研究員、本イベント・総合司会)